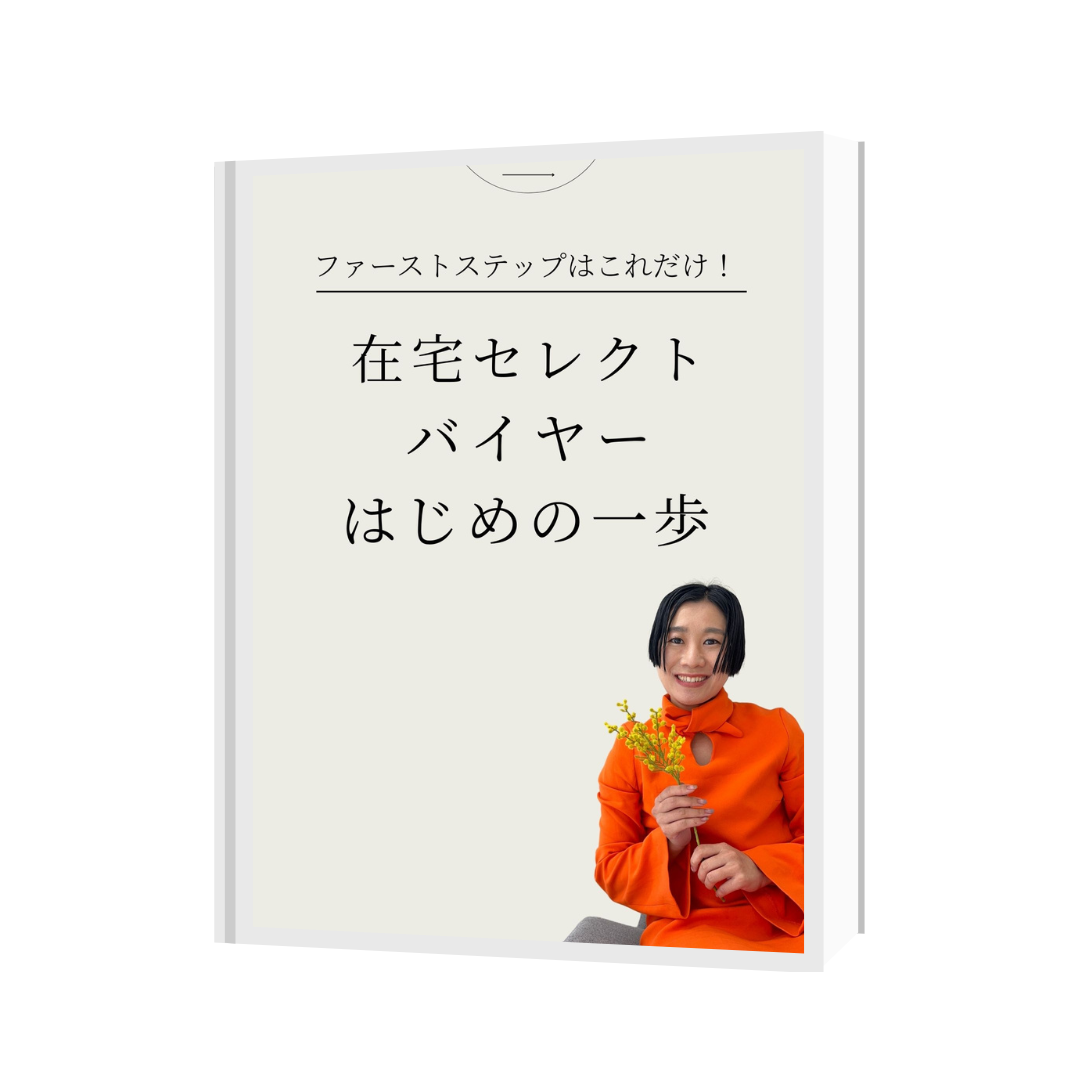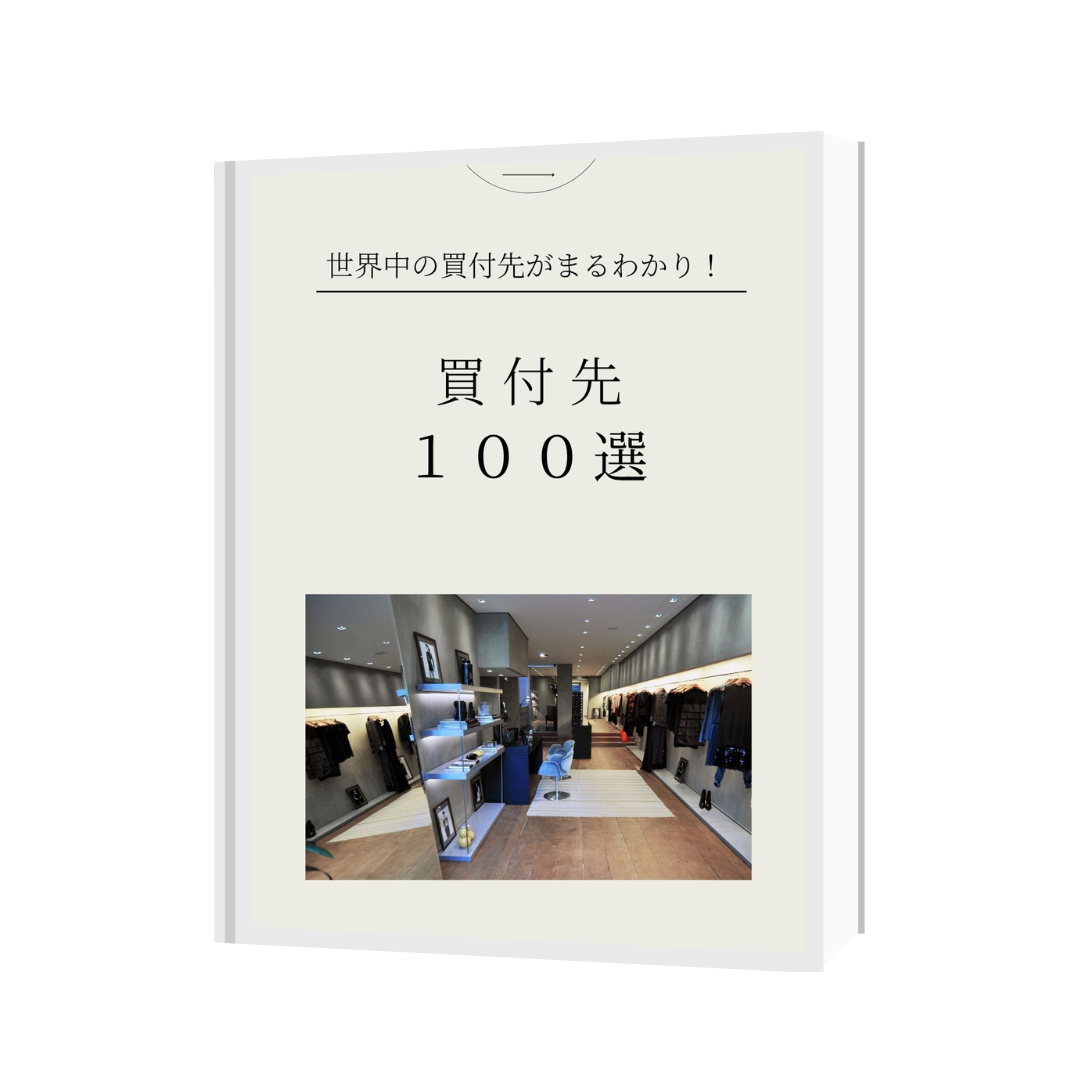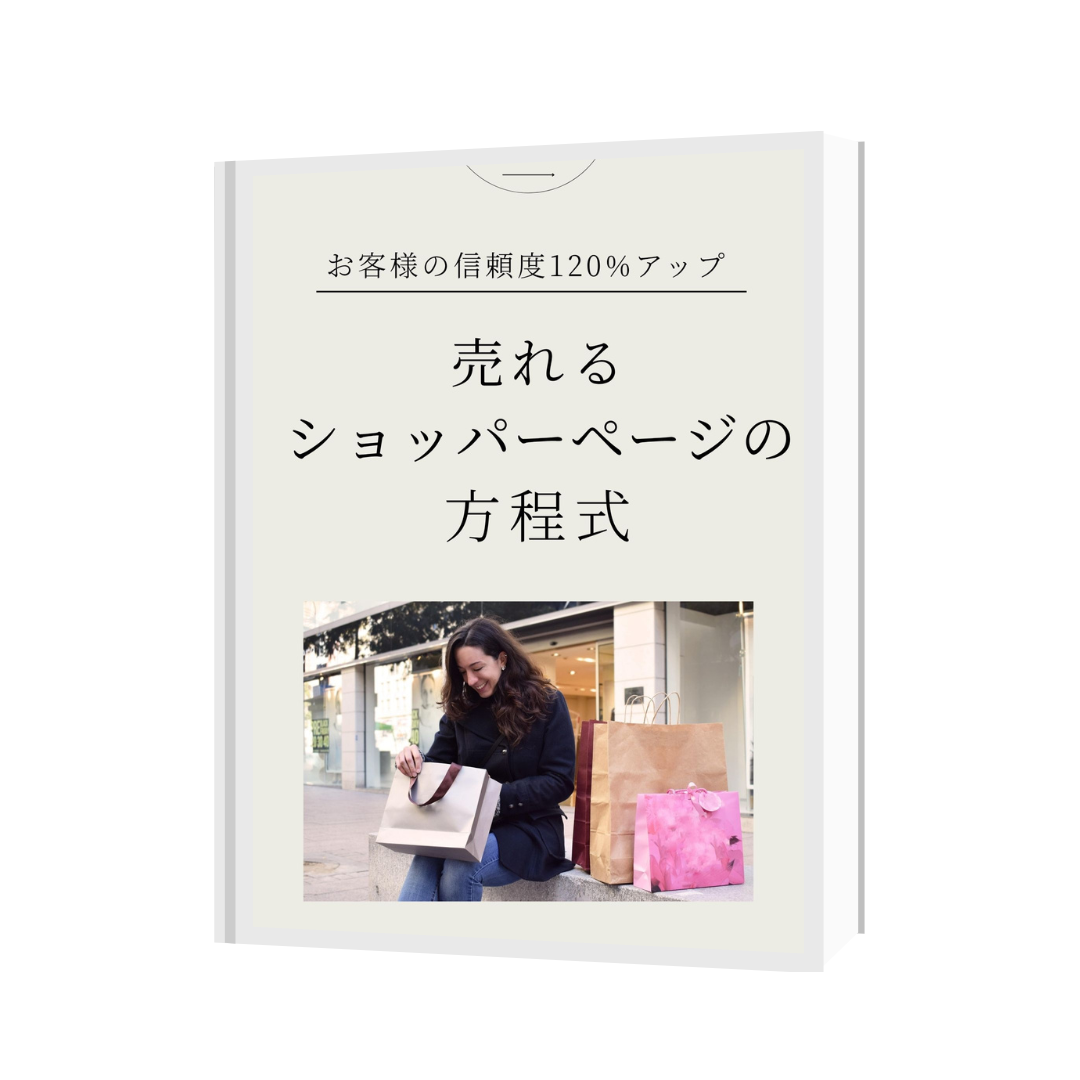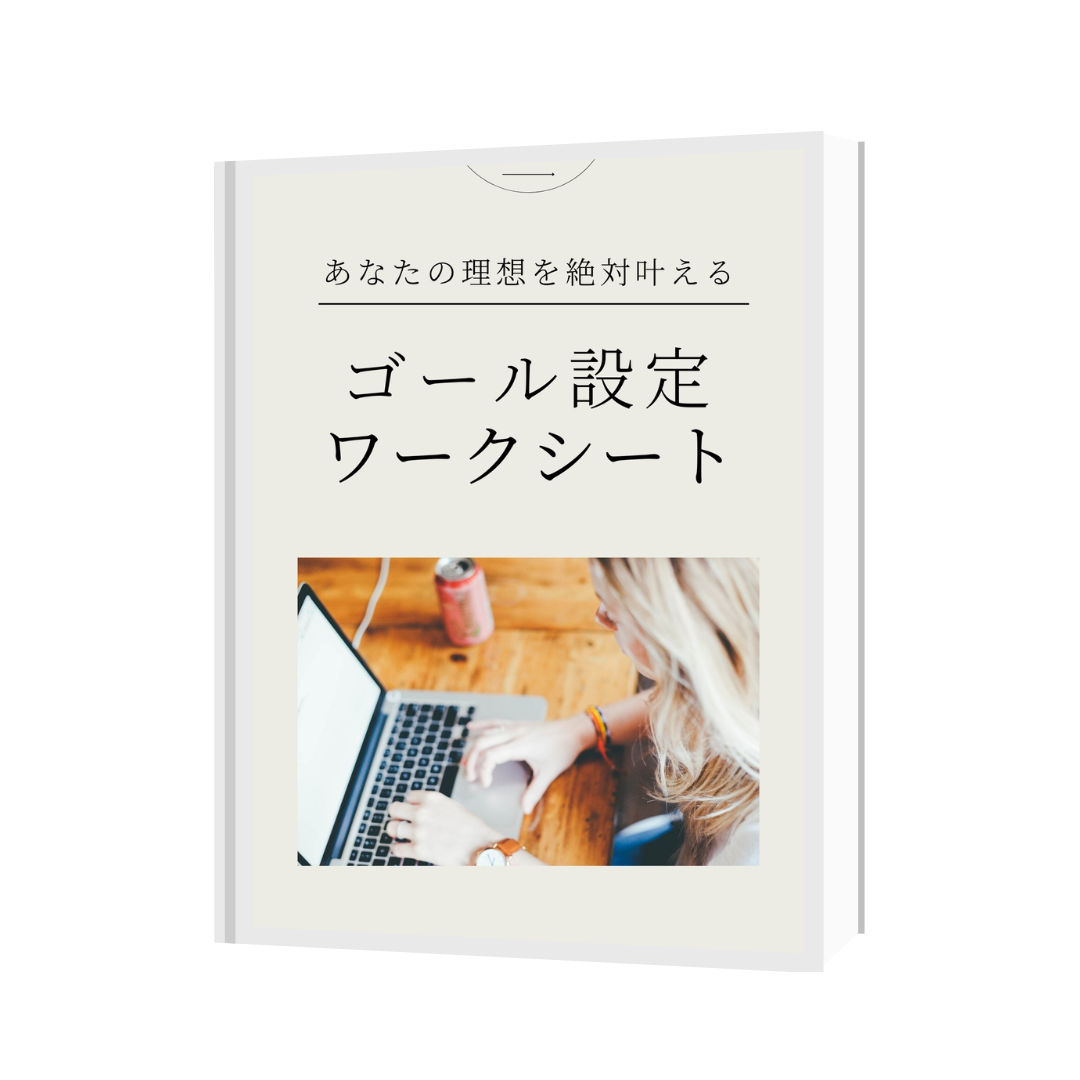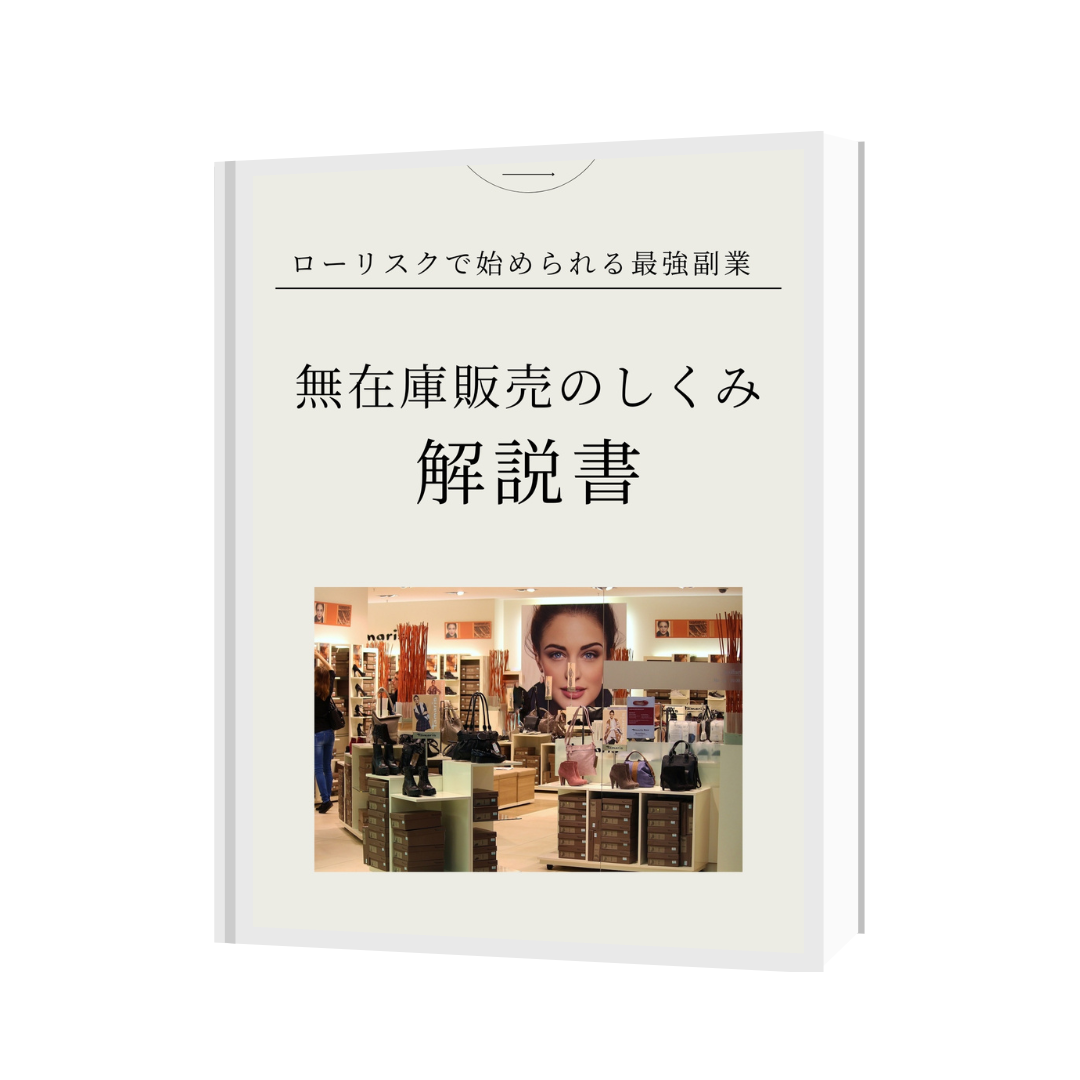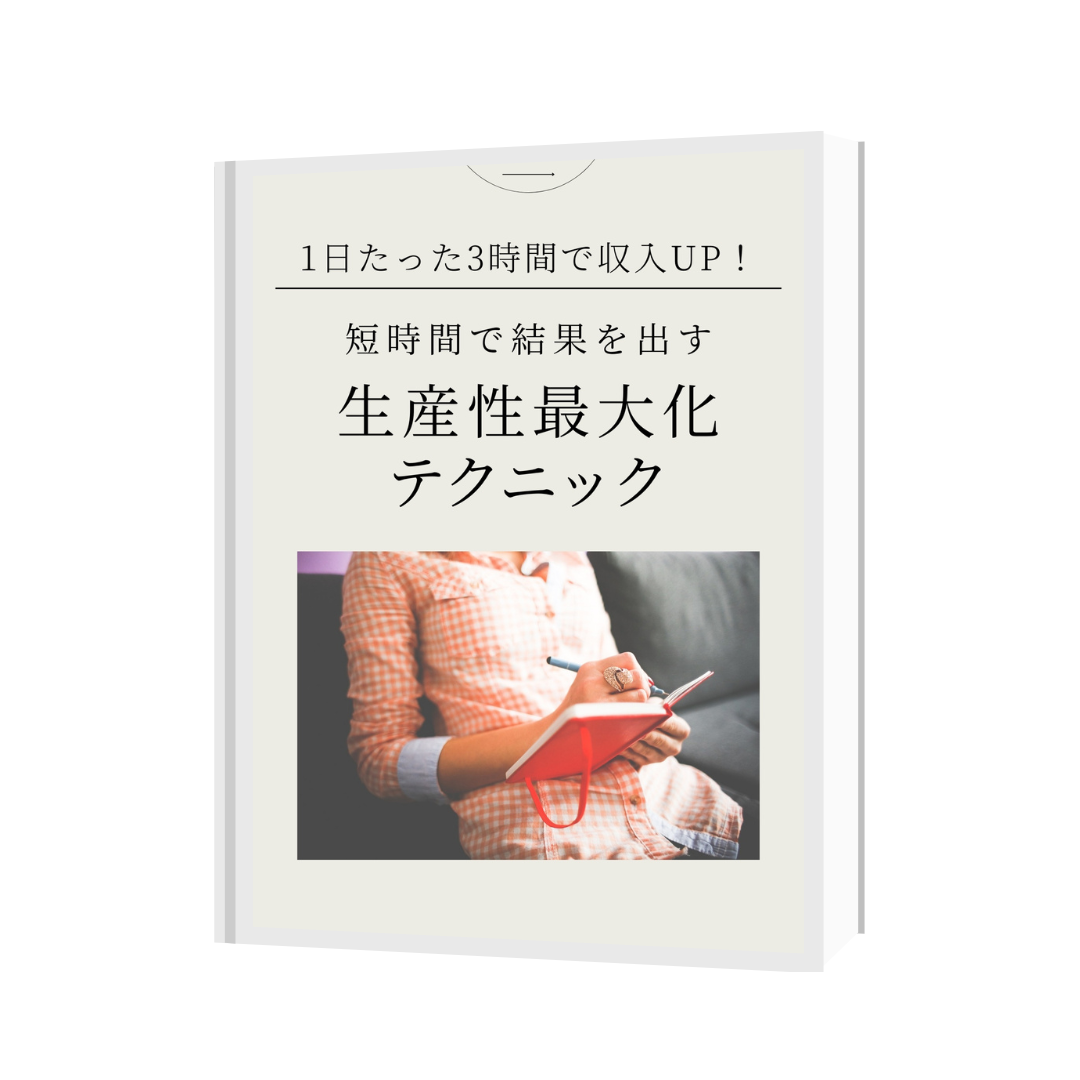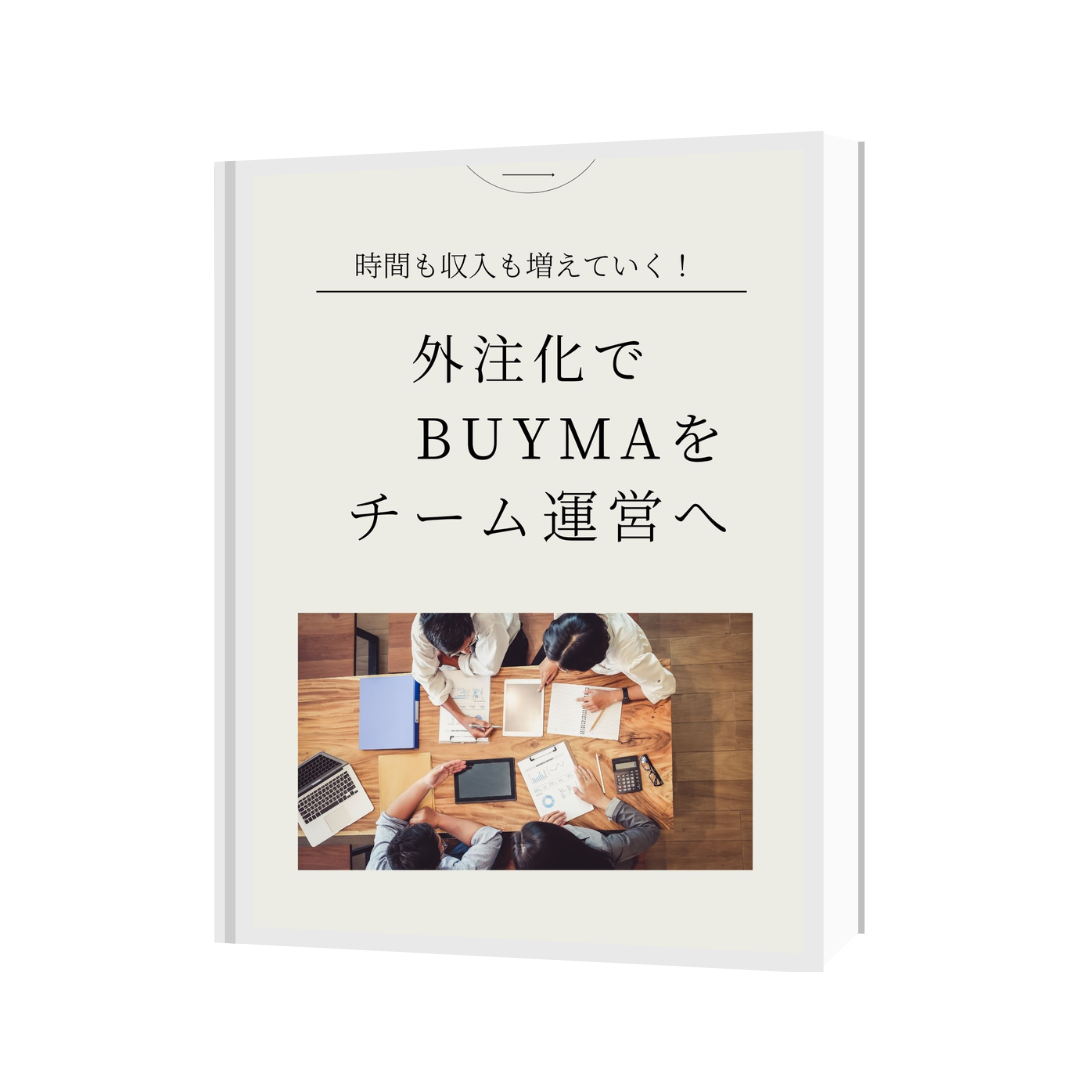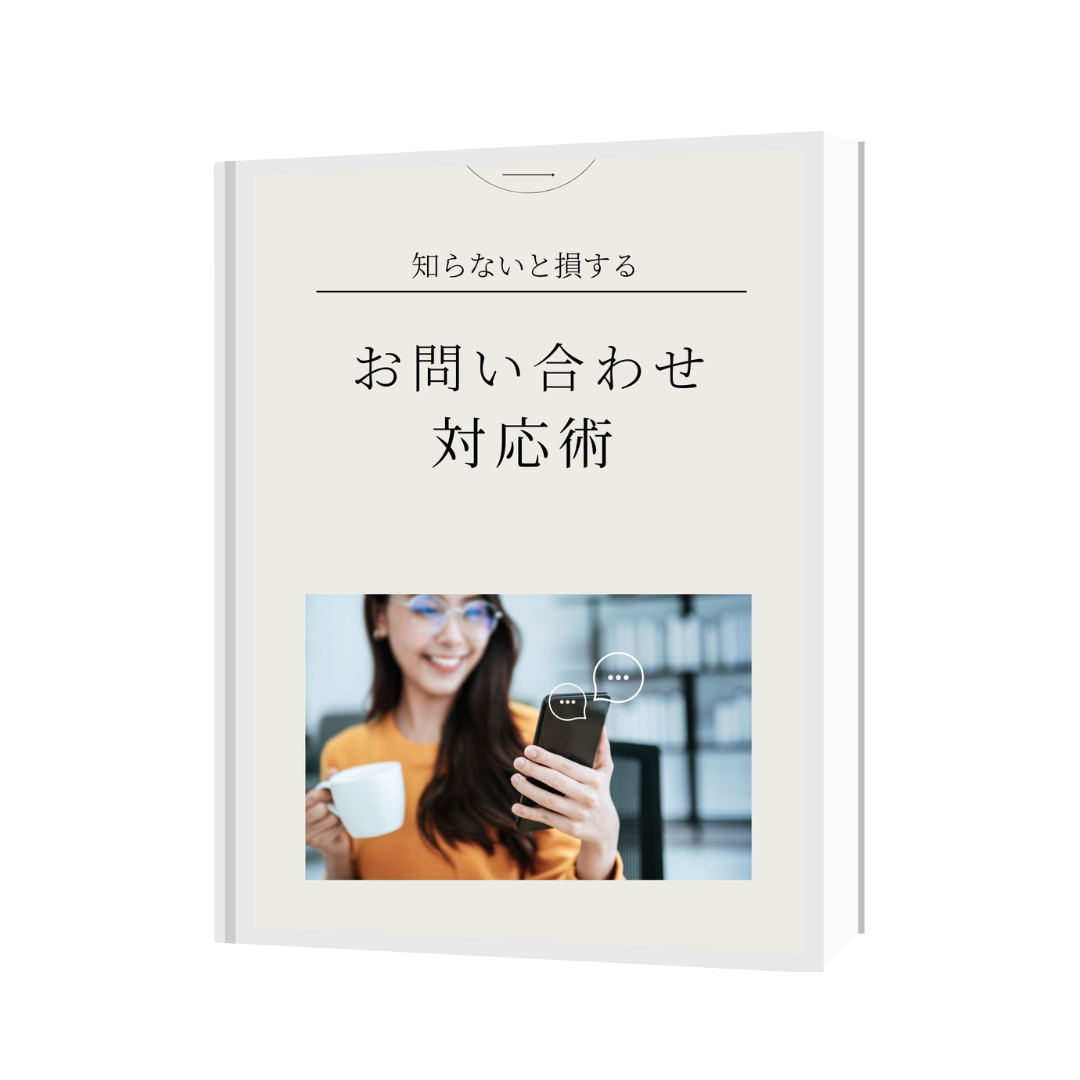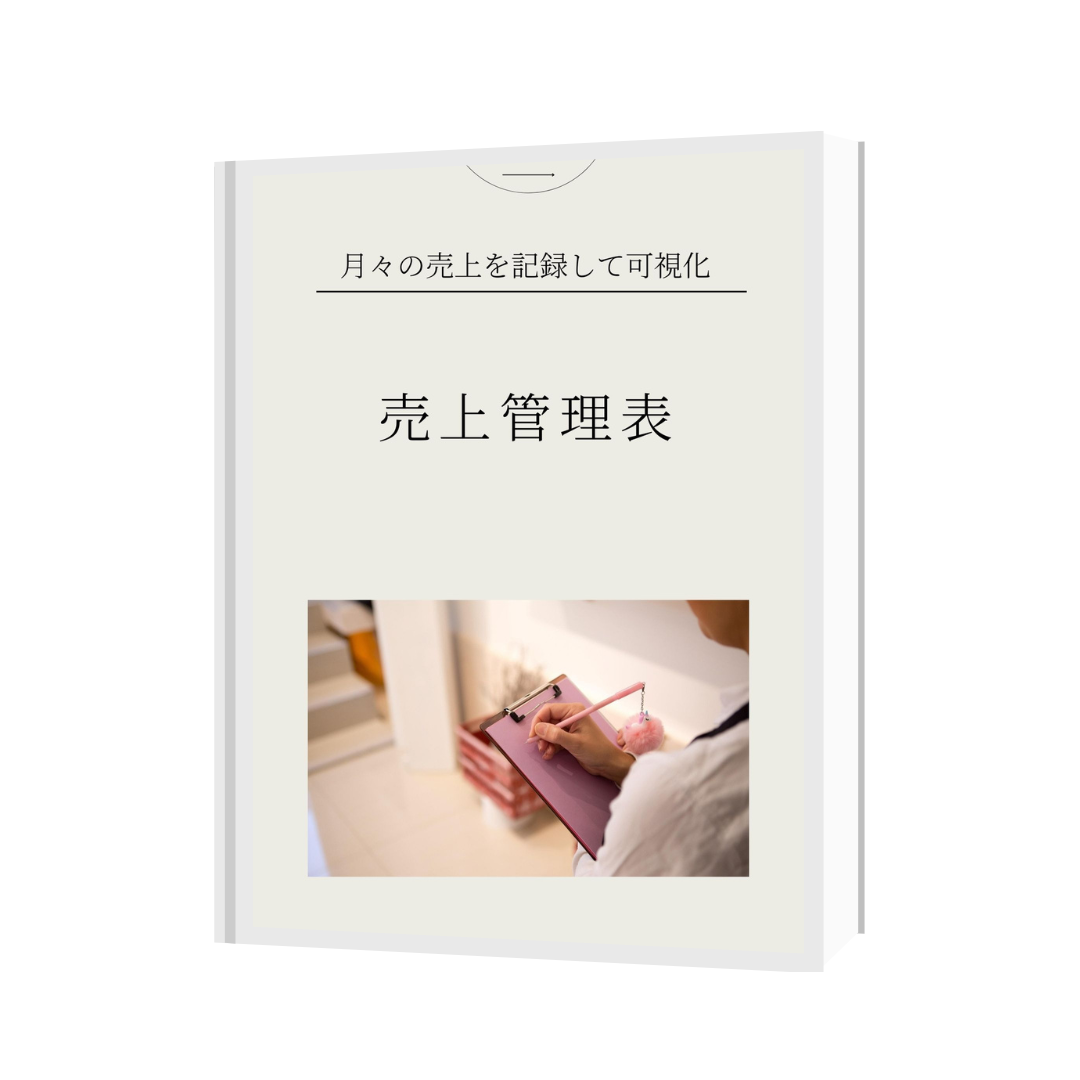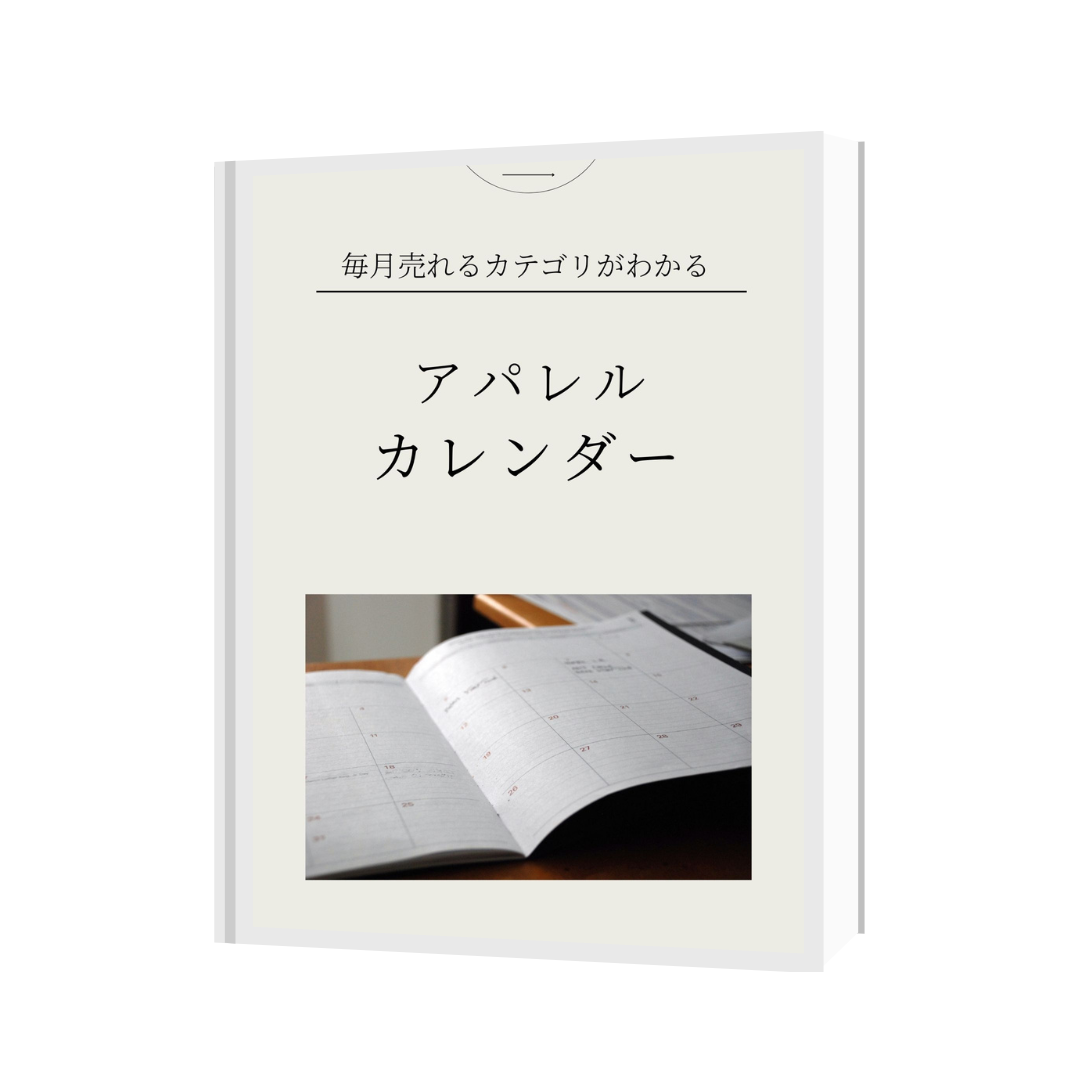- 最近のBUYMAの市場が大きく変化している……
- ハイブランドが売れにくくなった……
- ショップアカウントばかり優遇され、二極化が進んでいるのではないか……
そんな不安を抱えているBUYMAバイヤーの方も多いのではないでしょうか。こうした不安は、BUYMAを取り巻く市場の正確な「今」を知ることで解消できます。
この記事では、BUYMAの専門家として、現在BUYMAで何が起きているのか、そして個人バイヤーがこれから取るべき具体的な戦略について徹底解説します。
世界のラグジュアリー市場の変化とBUYMAへの影響
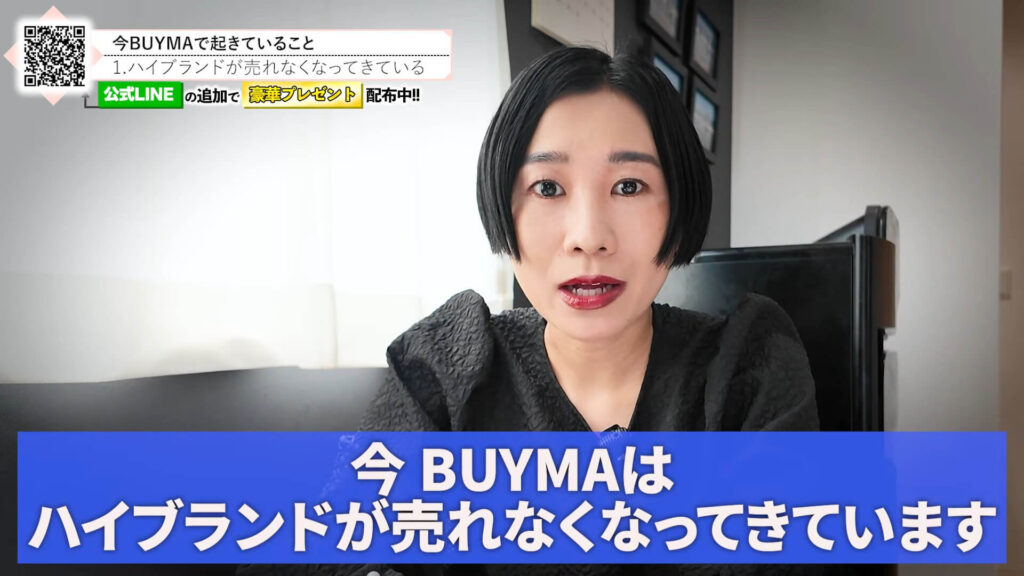
今、BUYMAだけでなく世界的にラグジュアリー市場が大きく変化しています。この変化は、BUYMAでの活動にも直接的な影響を与えています。
ハイブランドが売れなくなっている2つの理由
現在、BUYMAではハイブランドが売れなくなってきています。これはBUYMA特有の問題ではなく、業界全体の問題です。
日経新聞によれば、2025年の百貨店売上は6か月間減少が続いています。これは、去年よりも円安の影響が鈍くなって、アジア系のインバウンドが減っている環境要因も関係しています。
しかし、全体的に購入金額が減っており、これが売上減少につながっていることが指摘されています。
LVMHやケリングの売上減少が示す市場の冷え込み
世界的なラグジュアリーブランドの動向も、この変化を裏付けています。たとえば、ルイヴィトンやディオールを運営するLVMHは、2025年4月〜6月のファッション・レザーグッズの売上高が前年同期比で9%減となりました。
また、グッチなどを運営するケリングも同様です。fashionsnap.comによると、2025年1月〜6月期の売上は前年同期比15%減。ケリングの主軸であるグッチに至っては、売上高が25%減という深刻な状況です。
コロナ禍以降、ラグジュアリーブランドは何度も値上げをしたり、人気商品の生産を絞ったりと、ブランディングを強めてきました。それでうまくいっているブランドもありますが、全体としてラグジュアリーブランドの消費が減っているのです。

BUYMAでハイブランドが売れにくくなったのは、日本国内だけの現象ではありません。世界的なラグジュアリー消費の冷え込みが、そのままBUYMAにも影響していると捉えることが大切です
BUYMA内で起きている「二極化」の正体
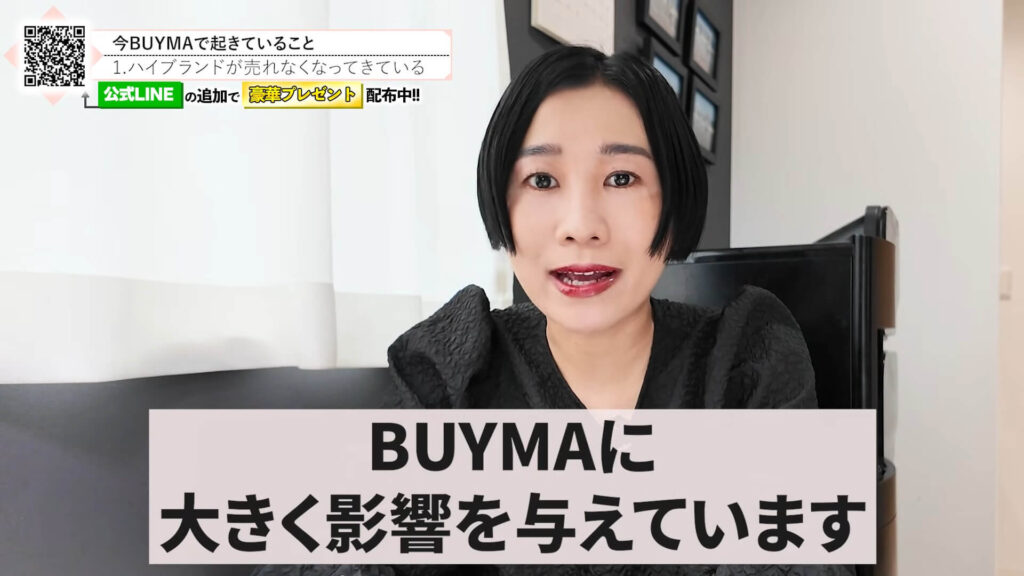
市場全体の変化に加え、BUYMA内部でも「二極化」という大きな構造変化が起きています。これは、個人の無在庫バイヤーにとって無視できない問題です。
なぜショッパーランキングに入りやすくなったのか
最近、BUYMAのショッパーランキング(レディースカテゴリー)では、売上500万円程度でもランクインできることが増えてきました。以前を知る人からすれば、レベルが下がったように見えるかもしれません。
しかし、これはレベルが下がったのではなく「二極化」が大きく進んだ結果です。売上500万程度でランクインしているのは、大体50位から100位の下層のバイヤーたちです。
一方で、ショップアカウントやプレミアムパーソナルショッパー(PPS)といった上位層のショッパーたちが、売上を大きく伸ばしています。その結果、一般ショッパーのシェアが取られ、ランキング下位のボーダーが下がっているのです。
ショップアカウント・PPSが優遇される実態
BUYMAを運営する株式会社エニグモの決算資料を見ても、ショップアカウントやPPSとの関係を強化する方針が明記されています。
実際に、彼らには個別の連絡があったり、限定の優遇サービスが提供されたりしています。最近マイページに表示されるようになった広告も、一部のショップアカウントやPPSには事前に案内がありました。
特に上位層のショッパーとは、BUYMAの事務局がミーティングをしたり、売れ筋商品の情報共有を行ったりしています。こうした取り組みが、現在の二極化をさらに加速させているのです。
なぜショッパーランキング上位を目指すべきではないのか
では、個人バイヤーもランキング上位を目指すべきなのでしょうか?
実は、BUYMAで上手に稼いでいる方は、このランキングの外でうまくやっています。
ランクインすると箔がつくと思うかもしれませんが、一目につきやすくなるため、モデリングもされやすくなります。そもそも、このランキングは「売上高」で決まるため、高額な商品を扱うバイヤーが必然的にランクインしやすい仕組みです。
ルイヴィトンやエルメスといったブランドでランクインしている人が、必ずしも多くないことからもわかる通りです。売上が高くても、実際には「薄利で」やっているアカウントも多く、ランキング=利益がしっかり取れている、とは限りません。

BUYMA内で二極化が進んでいるのは事実ですが、売上高だけを競うランキングを追いかける戦略は、個人バイヤーにとって最適とは限りません。大切なのは売上高ではなく、手元に残る利益です
BUYMA有在庫戦略の落とし穴|100万件超えの飽和状態
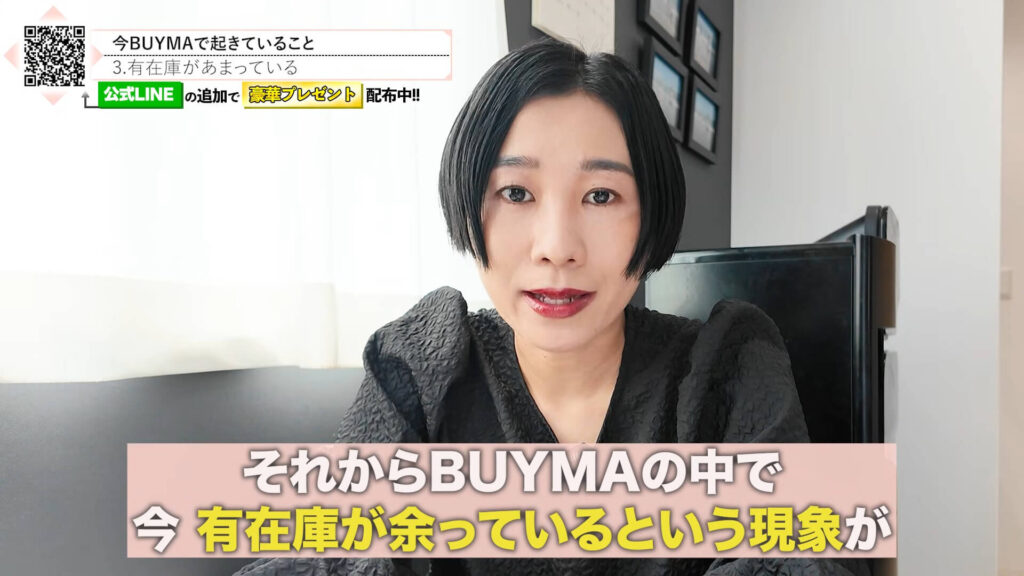
売上をカバーしようと、有在庫戦略に踏み切る人も増えましたが、ここにも大きな落とし穴があります。
なぜ有在庫を持つ人が急増したのか
有在庫を持つバイヤーは、ここ2〜3年で急激に増えました。コロナ禍の状況が落ち着き、売上が下がってきたのをカバーするためです。
また、有在庫はBUYMAの人気のアルゴリズムで優位に立てるという側面もありました。商品の実物画像を撮影し、青いチェックボックス(手元に在庫あり)をつけて出品することで、広告に載せてもらえるなど露出が強化されたからです。
著作権対策として、実物写真が必要だったという背景もあります。
資金ゲーム化する有在庫のリスク
しかし、その結果、現在のBUYMAは有在庫が飽和状態になっています。2024年9月現在、総出品数約570万件のうち、100万件が有在庫という状況です。
これは出品ページの数なので、サイズ違いや横積みの在庫を含めると、実際にはもっと膨大な数の有在庫が存在します。100万点と聞くだけでもゾッとする数です。
中身を分析すると、シーズンを過ぎたサンダルや夏物、売れそうにないカラーのバッグなど、不良在庫と化している商品も多く見受けられます。有在庫で利益を出すはずが、逆に自分の首を絞める結果になっているのです。
BUYMAは一品あたりが数万〜数十万円と高単価です。利益100万円を有在庫だけで達成したいなら、1,000万円近くの在庫を抱える必要があります。
リサーチの判断基準が甘いまま有在庫を持つのは、非常に危険な「資金ゲーム」なのです。

売上カバーやアルゴリズム対策として有在庫を持つバイヤーが急増し、市場は完全に飽和しています。リサーチが甘いまま有在庫を持つと、利益を出すどころか資金を失うリスクが高い状態です
今後のBUYMA戦略:注目すべきは「10万円以下のミドルブランド」
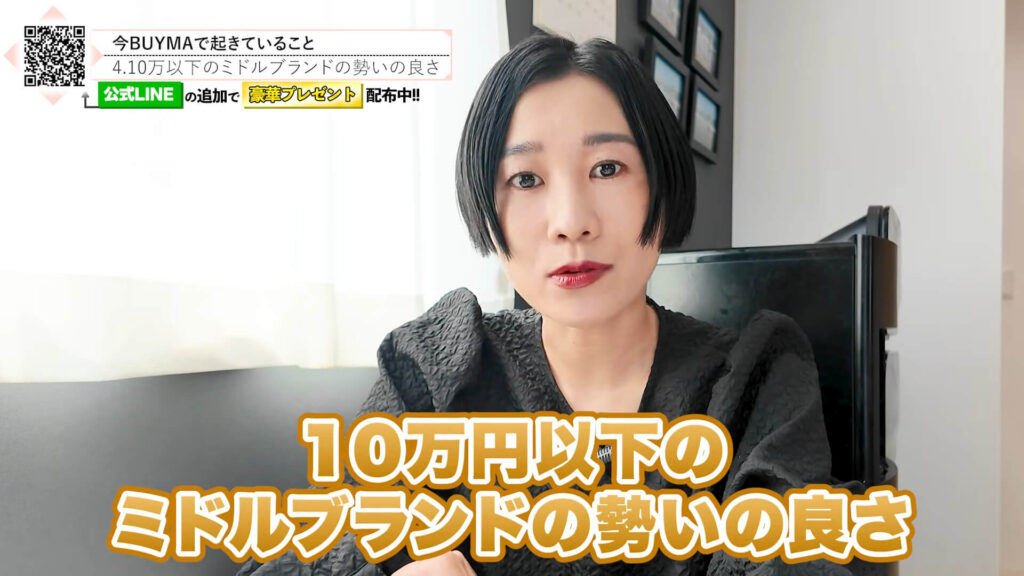
では、ハイブランドが失速し、有在庫も危険なら、個人バイヤーはどうすべきでしょうか。注目すべきは、市場の「視点」を変えることです。
ラグジュアリーからミドルブランドへの需要シフト
ハイブランドが売れないという状況は、環境要因であり変えられません。しかし、その分「10万円以下のミドルブランド」に目を向ければ、まだまだ戦えるというのが私の考えです。
先ほど、ランキングの外でうまくやっている人がいると言いましたが、そうしたバイヤーはこのミドルブランドをうまく取り入れています。
今の時代、特にZ世代と呼ばれる若い層は「みんなと同じ」よりも「自分だけの特別」を欲しがる傾向にあります。この「個の時代」のニーズをうまく汲み取っているブランドは、一般的に知られていなくても、ものすごく売れているのです。
中国・アジアブランドの台頭(オールドオーダー等)
具体的には、アメリカやイギリス、そして最近ではアジアのブランドが非常に強いです。特に中国ブランドには注目しています。
韓国ブランドの流行から、どんどんアジアのブランドがトレンドの中心になってきています。BUYMAのブランドランキングに入っている「オールドオーダー」や「アギュカルチャー」、あるいはトレンドキャラクターの「LABUBU(ラブブ)」なども中国発です。
希少価値とファン化(Chrome Hearts x Matty Boy)
また、アメリカブランドの「DENIM TEARS」なども高値で取引されています。ほかにも「Chrome Hearts」がアーティストの「Matty Boy」とコラボすると、即完売という状況が続いています。
即完売するからこそ、人は「どうしても欲しい」と殺到します。このように、希少価値を持たせてうまく「ファン化」が進んでいるブランドが、今のミドルブランドには多いのです。

ラグジュアリーブランドへの消費が落ち込んでいる一方で、「自分だけの特別」を求める「個の時代」のニーズは高まっています。この需要のシフトを捉え、ミドルブランドに注目することが今のBUYMA戦略の鍵となります
これからの時代に個人バイヤーが必要な2つのスキル
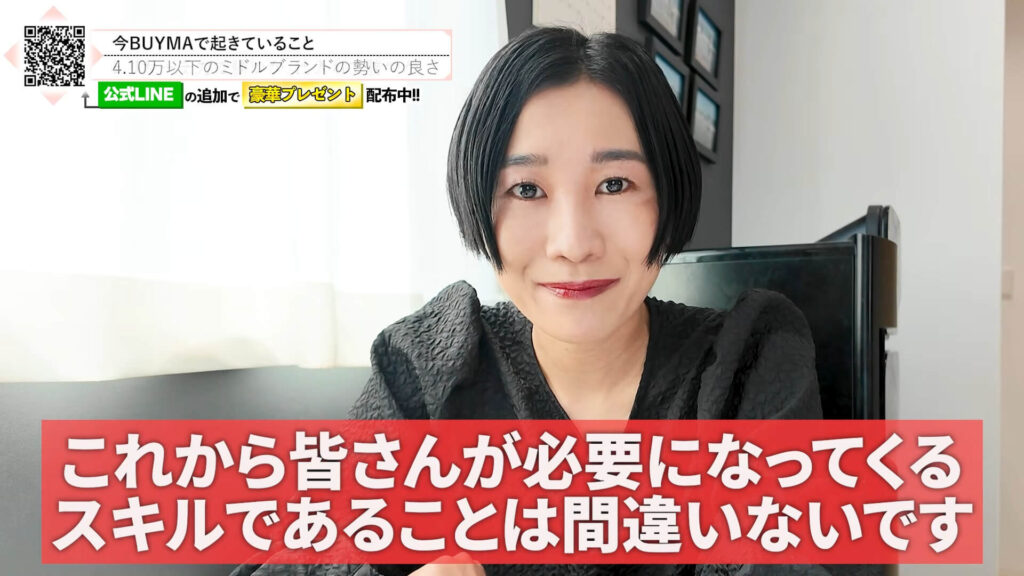
このようなトレンドの変化に対応し、BUYMAで稼ぎ続けるために必要なスキルは明確です。
トレンドを先読みし発掘する「リサーチ力」
BUYMAで稼いでいくために皆さんに必要なのは「リサーチ力」と「仕入れ力」です。この2つがないと、収入を増やしていくのははっきり言って難しいです。
特に、無在庫販売が中心の個人バイヤーにとっては、この「リサーチ力」を第一につけないといけません。常に新しいものを発掘し、販売していく、高いスキルが求められます。
利益を生み出す「仕入れ力」
「仕入れ力」については、BUYMAで売れる商品が増えてくれば、必然的に仕入れルートは拡大していきます。世界中に買い付け先を開拓していけば、活動を続ける中で自然と身につくスキルでもあります。
有在庫でうまくいっている方は、お店の数が多いというより、「深い繋がりのある仕入れ先」が1つ2つあるケースが多いです。リサーチ力で売れる商品を見つけ、仕入れ力で利益を確保する。この両輪が重要になります。

変化の激しい市場で継続的に稼ぐには、トレンドを発掘する「リサーチ力」が何よりも重要です。仕入れ力は後からでも強化できますが、まずは「何が売れるのか」を見つけるスキルを磨きましょう
まとめ:BUYMA市場の変化を捉え、戦略的に稼ぎ続けよう
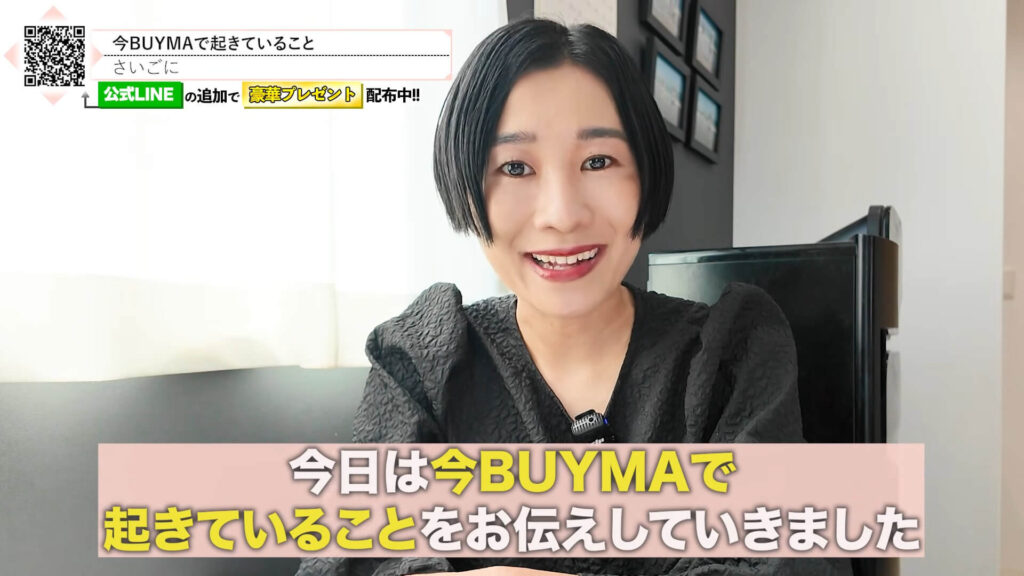
今回は、今BUYMAで起きている市場の変化について詳しく解説しました。ハイブランドの失速や二極化、有在庫の飽和など、不安になる情報もあったかもしれません。
しかし、大切なのは、こうした変化の波に乗りながら稼いでいくことです。ラグジュアリーが売れなくても、ミドルブランドに需要が移っているという事実に目を向けるべきです。
うまくいっている人は、常に新しい情報をキャッチして挑戦しています。市場の変化を恐れず、自分の戦略を見直すきっかけにしてください。